 近江商人
近江商人 見学できる商家
商家 住所 博物館名 備考 旧 藤井彦四郎邸 五個荘町宮荘681 五個荘町 歴史民俗資料館 旧 外村宇兵衛邸 五個荘町金堂645 近江商人屋敷 旧 外村繁邸 五個荘町金堂635 近江商人屋敷 旧中江正次邸 五個荘町金堂643 近江商人屋敷 ...
 近江商人
近江商人 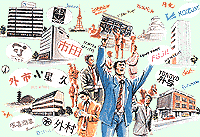 近江商人
近江商人 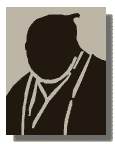 近江商人
近江商人  近江商人
近江商人 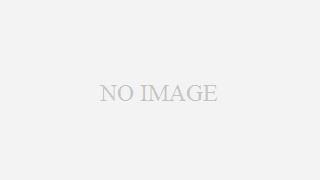 近江商人
近江商人  近江商人
近江商人  近江商人
近江商人 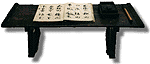 近江商人
近江商人  近江商人
近江商人 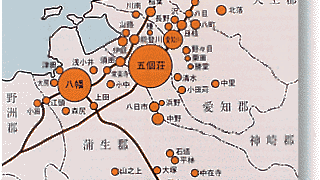 近江商人
近江商人