東嶺円慈(とうれいえんじ)
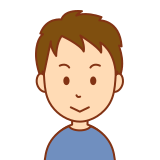
1721~1792
現五個荘町中出町に薬屋を営んでいた中村善左衛門の子として生まれる。9歳で能登川村大徳寺の亮山恵林について出家、17歳で古月禅材について修業し、その後白隠慧鶴の門に入る。白隠をたすけて伊豆三島の竜沢寺の創建に努めるなど近世を代表する禅僧の一人といえます。
野村文挙(のむらぶんきょ)
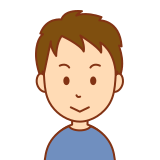
1854~1911
安政元年、神崎郡北庄(現 宮荘)の近江商人野村宇兵衛の長男として京都に生まれる。14歳で梅川東挙に学び、その後塩川文麟に師事、明治22年学習院教授となる。文挙の画は、円山四条派の写生画に近代的描法を加味し、近代的風景画のさきがけとして評価が高い。
山元春挙(やまもとしゅんきょ)
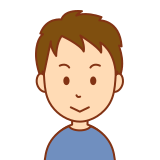
1871~1933
明治4年滋賀県膳所の山元善三郎の長男として生まれる。一時北五個荘村竜田の小杉家の養子となる。13歳で野村文挙に学ぶ。当時の京都画壇で、竹内栖鳳と並び称され、活躍しました。
外村繁(とのむらしげる)
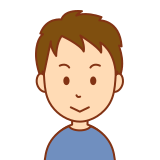
1902~1961
近江商人外村吉太郎の三男として南五個荘村金堂に生まれる。膳所中学、京都第三高等学校、東京帝国大学に進み、大正14年在学中に梶井基次郎・中谷孝雄らと同人雑誌「青空」を創刊する。昭和13年東京阿佐ヶ谷に居を移し、井伏鱒二・太宰治ら文士仲間と共に精力的に作家活動を行います。「筏」三部作は特に評価が高く、昭和31年には野間文芸賞を受賞しています。
その他当町ゆかりの文化人
| 建部伝内(たてべでんない) | 1522~1590 | 能書家 |
| 松村蒼石(まつむらそうせき) | 1887~1982 | 詩人 |
| 川島雄三(かわしまゆうぞう) | 1898~1986 | 彫刻家 |
| 外村吉之介(とのむらきちのすけ) | 1898~1993 | 倉敷民芸館 |
| 北村富三(きたむらとみぞう) | 1903~1956 | 洋画家 |
| 辻亮一(つじりょういち) | 1914~ | 作家 |
| 塚本邦雄(つかもとくにお) | 1922~ | 歌人 |

